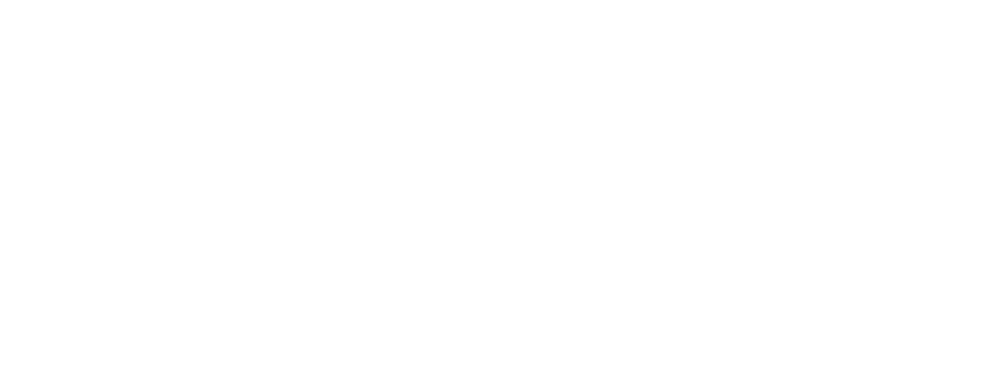菅野文さん×松崎史也さん 対談 【前編】
2013年から「月刊プリンセス」(秋田書店)に連載された「薔薇王の葬列」が、今年1月に本編完結を迎えた菅野文先生と、舞台「薔薇王の葬列」の演出・松崎史也さんが、初対談。シェイクスピアと演劇への深い愛を持つ二人は初対面で意気投合。熱い語り合いを前後編でお届けします。
リチャード三世の解像度が高すぎる
――松崎さんは、『薔薇王の葬列』を初めて読んだときにどのような感想を持ちましたか?
松崎 その話でずっと喋れてしまう(笑)。演劇をやっている人間からして、また僕はたまたまシェイクスピアを自分のプロジェクトでやっていたので、自分がやっているシェイクスピアのやり方っていうのが、特にシェイクスピアに触れてきていない、演劇にも触れてきていない、今その俳優を見に来ただけの人が見ても面白いものを作るっていうことをコンセプトにしているので、そこの部分に関して勝手ながら非常にシンパシーを感じて。
菅野 その通りです!私も『薔薇王』を描くときに、まさにそういう風に思って描き始めたので。そこをわかっていただいて嬉しいです。
松崎 シェイクスピアって、本当に素敵だし面白いんだけれども、今見ると退屈だとか、わけがわからないとか、キャッチーじゃないとかってなるところが、愛による工夫で描かれていたことに、演劇好き漫画好き両面から、非常に感動して嬉しくなりまして。今日はそのことをお伝えしたくて。
菅野 ありがとうございます。
松崎 本当に演出家冥利につきるような作品ですし、2.5次元もシェイクスピアもやっている自分が演出するのは巡り合わせだと強く感じて引き受けました。
――菅野先生は、演劇化の企画を聞いて最初にどう思われましたか?
菅野 そもそもシェイクスピアの『ヘンリー六世』の舞台を見て感動して作った漫画なので、舞台化されるというのは嬉しかったですし、楽しみだなと思いました。
松崎 『リチャード三世』は、僕もいずれやりたいなと思っていたんですけど、『薔薇王の葬列』でのアップデートのされ方の解像度が高すぎて。狡猾で残忍な稀代の悪役というイメージで知られるリチャード三世を、なぜ男女二つの性を持って生まれたことを秘密に抱える存在に設定したんですか? しかもそのことによって母親から愛されないということにしたことが、現代的な共感しやすい問題になっていて、そのアップデートのあとで、果たしてもう一度、背中の曲がったリチャードをやる意味があるのかな、と思うくらいにあまりにも鮮やかで、しかもエンターテインメントとしても強い変換だから素晴らしすぎる。
菅野 そもそも私は、前作でジェンダーをテーマにした『オトメン(乙男)』という作品も描いていて、そういうテーマをずっと描いていきたいというのがあって。でも、これっていうひとつの要素で語りきれない部分がありますね。ただ、リチャードの設定は変えようとは思ったんです。なぜなら原作の設定のままを漫画で描くのは制限があって無理だなと思ったので。設定を変えなきゃと思ったときに、プラトンの『饗宴』に出てくる男女両方の性が合わさったアンドロギュノスと呼ばれる存在が、完璧で頭がすごく良くて…。そういう部分がリチャードと通じるし、球体と言われていた形的にも通じるものがあって、それが浮かんだというか…。いろいろなものがかみ合ってこうなったという感じですね。
誰が観ても面白いものがエンターテインメント
松崎 納得です。大事な部分の一端を教えてくださりありがとうございます。シェイクスピア以外も舞台はご覧になるんですか?
菅野 子供のころから親が連れて行ってくれたりして、舞台には慣れ親しんでいました。でもよく観るようになったのは20代半ばの頃からです。きっかけは蜷川幸雄さんのシェイクスピア作品の『コリオレイナス』で、そこからミュージカルとかバレエとか何でもピンときたら観に行ってます。音楽もすごく好きでライブにもよく行くので、その延長線上で演劇も面白いなと。ドラマと映画も好きだったので、その生版だと思って。生だとやはり衝撃が違いますからね。
松崎 そうですよね。
菅野 観るたびに違うから、何回も観ちゃうんですよ(笑)。蜷川さんのシェイクスピア『ヘンリー六世』も十何回か観ました。
松崎 『薔薇王の葬列』のこの解像度の高さは…?と、すごく不思議だったんですけど、納得です!
菅野 ハハハハ。やっぱりすごく面白いんですよ、演劇って。
――やはり、特にシェイクスピアが面白いと思いますか?
菅野 ひとつのタイトルで演出家によってぜんぜん違うアプローチの作品を楽しめるので、漫画家としてお話を作る自分にとっては、いろいろな人の解釈を見られるのはすごく面白くて。「なんだろう? この演出」みたいなものもありますけど、すごく有名な人とかでも。最近は若い人が演出している作品が面白いなってよく思います。
松崎 そうなんですよ。演劇のほうはもうシェイクスピアはやりつくしていたり、周りからの期待とかもあったりで、誰に何を見せようとしているのか?っていう方向になっていっちゃうんですよね。
菅野 そうですね。『ヘンリー六世』を初めて観たときに、その頃はその時代の歴史にあまり詳しくなかったので、ものすごく長いし、途中でちょっと寝ちゃったりもして(笑)。でも最後まで観てすごく面白かったなと思って。
松崎 わかります(笑)。
――少し知識を入れて行ったほうが楽しめるのでしょうか?
松崎 いや僕は、始めに言ったように、ある程度誰が観ても口当たりのいい普通の人が見て面白いものが、エンターテインメントであるべきだと思っているし、対価をいただいていいものだと思っているから。一部のリテラシーの高い方々とか教養の高い方々が、したり顔で観るものみたいになっていけばいくほど、よくないとは思っている。眠くならないほうがいいと思っていますよ(笑)。
菅野 あと、『リチャード三世』でもそうですけど、女性をややディスるような冗談が入ったりするんです。けど、私にとっては全然面白くない。会場でも2人くらいしか笑ってないんですよ。そういうのも嫌だったので、現代版として、いろいろな人が面白く観られる要素を入れたいし、逆にシェイクスピアがやれていなかった部分を描けたらいいなと思って。それは『薔薇王の葬列』ではけっこう意識して。キャラクターの台詞でも言わせる人をわざと変えたりとか、女性と男性を少し逆にするとか。
松崎 マーガレットの台詞は最高です。
菅野 マーガレットは本当にいいキャラなんですよ。史実がああいう感じなので、一番改変がなくてもいいキャラクターだから。
――最高なのはどんな台詞ですか?
松崎 アンにかけている言葉で、「男の肋骨から造られた女が人を宿し産むことができるのは何故だと思う? 男から自分の運命をとり戻す為よ」っていう。やっぱり女性の作家が力強く書いてそれがカッコいいってことは、すごくカッコいいことだなって思うし。それを女優がまた舞台上で言うっていうことも、素晴らしいことだなと思うし。
菅野 そこは、母親になっている友達や自分の母親も含めた周りの女性たちを見たり、話したりしているなかで、そういうふうに思ったんじゃないかなと感じたんです。だから、作中に登場する母親や女性の言葉は、私というよりは、周りの女性たち母親たちの言葉というか…。それを代弁者として キャラに言ってもらったという感じがあって。そういう意味では、この台詞に限らず、どんな立場のキャラでも客観的に描いたところと主観が入っているところはありますね。